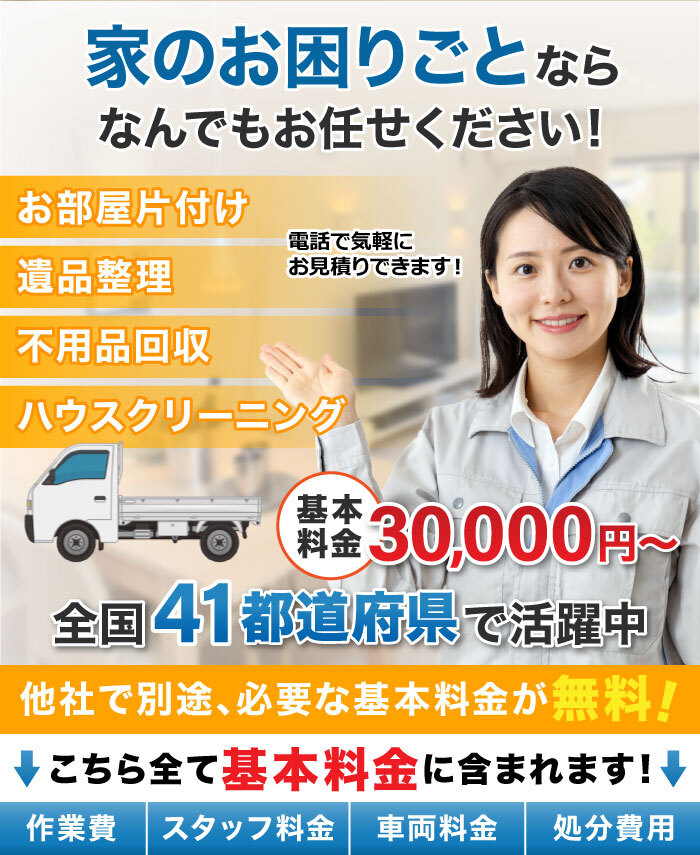相続放棄を考えている方の中には、「遺品整理をしても大丈夫なのか」「故人が連帯保証人だった契約はどうなるのか」と不安を抱える方が多くいらっしゃいます。相続放棄には厳しいルールがあり、間違った対応をすると相続を認めたと判断され、借金や保証債務まで引き継いでしまう恐れがあります。また、賃貸物件の残置物や原状回復など、相続放棄後にも対応が必要なケースもあります。
この記事では、相続放棄と遺品整理、連帯保証人が関係する場面について、法律上のポイントを分かりやすく解説し、正しい対処法をお伝えいたします。
相続放棄前に注意すべき遺品整理の基本ルール

相続放棄を考えている場合、むやみに遺品に触れると相続を承認したとみなされる危険があります。相続放棄が成立するまでは、遺品整理の範囲が法律で厳しく決まっているため、正しい知識を持つことが安心につながります。
相続放棄中に遺品を触ると“単純承認”になる理由
相続放棄中に遺品を触ると危険だとされるのは、民法で「相続財産を処分すると相続を承認したとみなされる」と定められているためです。なぜなら、財産を売ったり、持ち帰ったり、手続きに使ったりすると、法律上は“自分の財産として扱った”と判断されるからです。
また、単純承認になると、相続放棄は認められず、借金や保証債務も含めてすべて相続することになります。さらに、一度単純承認が成立すると、あとから取り消すことはほとんどできません。そのため、相続放棄を検討している場合は、遺品に触れる行動がどこまで許されるのかを正しく知ることが重要です。
特に価値のある物を動かしたり、契約名義の変更や引き落としに関わる行為は単純承認と判断されやすいため、避けなければなりません。相続放棄中は、「遺品に触らないことが基本」という意識を持ち、迷ったときは専門家に相談することが安全な対応となります。
相続放棄が認められない行為とは何か
相続放棄が認められなくなる行為には法律上明確な基準があり、その中心は「相続財産を自分の財産のように扱う行為」です。たとえば、故人の預金を引き出して費用を払う、現金や貴金属を売却してしまう、価値のある家財を引き取るといった行動は、相続を承認したと判断されやすくなります。
また、故人名義の携帯電話や各種サービスを相続人自身が解約することも、財産処分にあたる可能性があります。さらに、故人が住んでいた賃貸の契約を相続人が主体となって解約した場合も「財産の処分」に該当し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これらの行為は、善意で行った場合でも法律上は相続承認として扱われ、あとから「相続放棄したかった」と申し出ても認められないことがあります。そのため、相続放棄を考えている段階では、少しでも財産処分につながる行為は慎重に避けることが必要です。
手を付けてもよい「最低限の整理」の範囲
相続放棄中でも、すべての物に触れてはいけないわけではありません。法律上、生活や衛生に関わる最低限の整理は認められています。具体例としては、腐敗する食品や生ごみの処分、危険物の除去、悪臭や害虫が出るような明らかな衛生リスクへの対応が挙げられます。
また、写真・手紙などの価値がない思い出品の確認や簡単な形見分けは、財産的価値がないため単純承認にはあたりません。さらに、火災や漏電の危険がある場合の点検や応急的な片付けなど、安全確保のための行為は必要な管理行為として認められています。
ただし、この範囲を超えると相続放棄が否定される可能性があるため、「価値のあるものは動かさない」「契約・金銭に関わる物には触れない」という原則を守ることが大切です。迷った判断を避け、必ず専門家に確認しながら進めることが安全です。
相続放棄中にやってはいけない具体的なNG行為

相続放棄を進める期間中は、相続人が故人の財産に関わる行動を取ると、法律上「相続を承認した」と判断される恐れがあります。特に財産価値のある物の処分や契約への介入は単純承認とみなされるため、慎重な行動が求められます。
財産価値のある遺品を売却・処分する
財産価値のある遺品を売却したり処分したりすることは、相続放棄の手続き中であっても「相続を承認した」と判断される大きな理由になります。その理由は、民法において財産の処分行為は単純承認に該当すると明確に定められているためです。
たとえば、貴金属、ブランド品、パソコン、家電、収集価値のある物などを売却した場合、たとえそのお金を相続人自身が使っていなくても、法律上は相続財産を自分のものとして扱ったと判断されます。また、廃棄するだけであっても、価値のある財産を相続人が主体となって処分したと見なされる可能性があります。
その結果、相続放棄の申述が認められず、故人の借金や保証債務を含むすべての相続を引き継ぐことになってしまいます。相続放棄中は「価値のある物には触れない」という意識が必要で、どうしても判断に迷うときは専門家へ相談することが安全につながります。
故人名義の契約・口座に相続人が介入する
故人名義の契約や口座に相続人が介入する行為も、相続放棄を続ける上で大きなリスクとなります。理由として、名義変更や解約、預金の引き出しなどは財産の管理や処分に深く関わる行為と見なされ、法律上“単純承認”と判断される可能性が高いからです。
たとえば、故人の携帯電話やインターネット契約を相続人が自ら解約する、公共料金の契約を停止する、クレジットカードを解約するなどの行動は、契約内容の扱いに関与したとみなされます。また、故人の銀行口座からお金を動かす行為は特に危険で、葬儀費用や生活費などの支払い目的であっても「相続財産の処分」と判断されます。
これらの行為をしてしまうと相続放棄の申述が認められず、多額の借金や保証債務を相続してしまう可能性があります。相続放棄中は、故人名義の契約や口座については自分で触らず、専門家に相談しながら慎重に対応することが重要です。
賃貸物件の解約や清掃を相続人が進める
賃貸物件に住んでいた故人の部屋を相続人が解約したり清掃したりする行為は、相続放棄中に特に注意しなければならないNG行為です。その理由は、賃貸契約の解約や部屋の原状回復に関わる行動が、財産処分に該当する可能性が高いからです。
たとえば、相続人が管理会社と解約日を決めたり、残置物を片付けたり、鍵を返却したりすると、その賃貸契約に直接関与したとみなされ、結果として相続を承認したと判断される恐れがあります。さらに、部屋の清掃や不用品の処分を相続人の判断で行うことも、相続財産の処分に該当する可能性があります。
これらの行為を行うと、相続放棄が認められず、賃料の未払い分や原状回復費用を相続人が負担しなければならない状況に陥ることがあります。賃貸物件の対応は特に複雑なため、相続放棄中は自分で動かず、専門家や管理会社と適切に連携しながら慎重に対応することが必要です。
相続放棄後でも遺品整理の義務が残るケース

相続放棄をしても、状況によっては遺品整理や部屋の処理を避けられない場合があります。特に連帯保証人としての責任や、法律上の管理義務が発生するケースでは、相続放棄とは別の理由で行動が必要になります。
相続人自身が連帯保証人の場合に残る責任
相続人自身が故人の契約に対して連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしてもその責任が消えない場合があります。その理由は、連帯保証契約が「相続とは別に成立している個人の契約」だからです。たとえば、故人が賃貸物件に住んでいて、相続人がその契約の連帯保証人だった場合、未払い家賃や退去時の原状回復費用の請求が相続人に直接届く可能性があります。
また、家財の撤去費用や鍵の返却など、賃貸契約を終了させるための手続きも連帯保証人として対応しなければならないことがあります。このように、相続放棄をしても連帯保証契約は継続するため、遺品整理や残置物処理を全く無関係に避けることはできません。
連帯保証人になっているかどうか、契約書や管理会社への確認が非常に重要であり、責任を正しく把握することで無用なトラブルを防ぐことができます。
相続財産の管理義務が生じる場合
相続人が相続放棄をしたとしても、相続財産の管理義務が生じることがあります。その理由は、民法で「相続人は次の相続人が決まるまで財産を適切に管理する義務がある」と定められているためです。たとえば、家の中に残された物が腐敗して悪臭が出る、雨漏りや火災などの危険がある、または近隣トラブルにつながるような状態が放置されている場合、相続放棄をした相続人でも必要な管理行為を求められる可能性があります。
これは遺品整理の一部を行うことにつながる場合もありますが、あくまで「管理行為」の範囲に限られ、財産価値のある物の売却や処分とは異なります。また、相続財産管理人が選任されるまでの一時的な対応として行うものであり、相続を承認したことにはなりません。
管理義務が発生するケースでは、必要な対応とやってはいけない行為の境界線を理解し、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
孤独死などで原状回復が必要になる場合
孤独死が発生した賃貸物件では、相続放棄をしても原状回復が必要になるケースがあります。理由として、故人の死亡によって部屋が損傷したり、特殊清掃が必要になった場合、賃貸契約の責任が契約者や連帯保証人に残る可能性があるためです。
たとえば、体液や臭気によって床や壁が傷んでいる場合、通常の清掃では対応できず、専門的な原状回復作業が必要になります。この費用は、相続人ではなく連帯保証人が支払う義務を負うことがあります。そのため、相続放棄をしても「賃貸契約に基づく責任としての原状回復」が求められる点に注意が必要です。
また、部屋の状態が著しく悪化している場合、放置すると近隣トラブルや衛生問題につながるため、管理会社との連携が欠かせません。こうした状況では、遺品整理業者や特殊清掃業者と専門家のサポートを受けることが、安全で確実な対応につながります。
故人が連帯保証人だった場合に相続放棄で何が変わる?

故人が生前に連帯保証人となっていた場合、相続放棄をしても状況によっては責任から完全に離れられないことがあります。連帯保証契約の性質や保証内容によって相続人の負担が変わるため、正しい仕組みを理解することが重要です。
故人の連帯保証債務は原則として相続の対象
故人が連帯保証人だった場合、その保証債務は原則として相続の対象になります。理由は、連帯保証契約も故人の「債務」に含まれるため、借金と同じ扱いで相続されるからです。たとえば、故人が友人や家族の借金の保証人になっていた場合、その返済が滞ると連帯保証人である故人に支払い義務が発生します。
そして故人が亡くなれば、その支払い義務は相続人に引き継がれることになります。しかし、相続放棄をすれば、この連帯保証債務も含めて一切の債権・債務を引き継がずに済みます。この点は「故人自身の財産に結びついた負担であれば放棄できる」という相続制度の仕組みによるものです。
ただし、保証債務の内容が複雑な場合や、保証契約の履行が始まっていた場合などは注意が必要です。相続放棄をすることで法律上の支払い義務はなくなるものの、貸主や債権者から問い合わせが来る可能性もあるため、手続きの前後で専門家の助言を受けることが安全につながります。
保証契約の種類によって変わる相続人の負担
連帯保証契約にはさまざまな種類があり、どの契約に該当するかによって相続人の負担が大きく変わります。たとえば、借金の保証、賃貸契約の保証、事業融資の保証など、目的によって保証内容が異なります。特に賃貸契約の保証では、家賃の未払いだけでなく、退去時の原状回復費用や残置物撤去費など、付随する支払いが広範囲に及ぶことがあります。
一方、相続放棄をすればこれらの負担はすべて相続人から切り離され、法律上支払う義務はなくなります。しかし、保証契約の種類によっては、貸主が相続人に状況確認や鍵の返却などの協力を求める場合もあります。
また、故人自身が事業関連で保証人になっていた場合は、債権者からの連絡が複雑になりやすく、適切な対応が求められます。このように、保証契約の内容によって相続人の対応範囲が変わるため、契約内容を確認し、相続放棄の効果がどこまで及ぶのか専門家に相談しながら理解することが重要です。
貸主・管理会社から残置物撤去を求められた際の対応
故人が住んでいた賃貸物件で、貸主や管理会社から残置物の撤去を求められるケースは珍しくありません。その際、相続放棄をした相続人が対応すべきかどうかは、契約と法的義務を正しく理解することが重要です。相続放棄をしていれば、残置物の処分や費用を支払う義務は原則ありません。
しかし、貸主が「相続人が責任を負うべき」と誤って案内してくる場合もあります。このような場合は、相続放棄を証明する書類を提示し、「相続財産管理人が選任されるまで対応できない」ことを明確に伝えるのが適切です。
また、残置物の放置が長引くと、管理会社が強制撤去を進め、その費用を相続財産に請求することがあります。そのため、貸主とのやり取りでは無用な誤解を避けるために、専門家のサポートを受けることが望まれます。相続放棄後も、正しい知識と適切な対応によってトラブルを回避することができます。
連帯保証人トラブルを避けるための実務的ステップ

連帯保証人が関係する相続問題は、契約内容の確認や正しい手続きが重要です。特に賃貸契約や保証契約は複雑で誤解が生まれやすいため、事前に情報を整理し、適切な対応を進めることがトラブル回避につながります。
賃貸契約・保証契約の内容を正確に確認する
連帯保証人に関するトラブルを避けるためには、まず故人が結んでいた賃貸契約や保証契約の内容を正確に把握することが大切です。その理由は、契約書に書かれている条文によって相続人がどこまで関係するかが大きく変わるからです。
たとえば、賃貸契約では家賃だけでなく、原状回復費用、鍵交換費用、残置物撤去の扱いなど、保証範囲が広く設定されている場合があります。また、借金の保証契約では、「極度額」や「保証期間」などの条件によって負担が変わります。
相続放棄をする予定でも、契約内容を知らないままでは、貸主からの要求に誤った対応をしてしまうことがあります。契約書を確認するときは、記載されている項目だけでなく、特記事項や付帯契約も含めて総合的に把握することが必要です。不明点がある場合は、そのまま判断せず専門家に相談することで、無用なトラブルを避けることができます。
貸主・債権者への正しい通知と交渉ポイント
貸主や債権者への連絡を正しく行うことは、連帯保証人に関するトラブルを防ぐうえでとても重要です。理由は、相続放棄をしても相手側がその情報を知らなければ、相続人に請求を続けてしまうことがあるためです。まず、相続放棄が受理されたら、その書類をコピーして貸主や債権者に提出し、「相続財産の管理人が決まるまで対応できない」ことを明確に伝えることが必要です。
このとき、感情的にならず事務的に対応することで、不必要な誤解を防げます。また、貸主からの要請が法的に正しいのか判断できない場面もあります。その場合は、すぐに返答せず、内容を確認してから慎重に返事をすることが重要です。
相手が誤った請求をしている場合でも、しっかりと法律に基づいて丁寧に説明すれば、多くの場合は問題なく話を進めることが可能です。正しい通知と交渉の姿勢が、トラブルを大きくしないための鍵になります。
請求が妥当かどうか判断するための基準
貸主や債権者から請求が届いた場合、その内容が妥当かどうかを判断することがとても大切です。理由は、不当な請求に応じてしまうと、本来支払う必要のない費用まで負担してしまう恐れがあるためです。賃貸契約の原状回復費用の場合、国土交通省のガイドラインに沿って判断することが重要で、経年劣化による傷みは入居者の負担になりません。
また、残置物撤去費用が高額な場合は、見積書の内容や作業範囲を細かく確認し、不明瞭な請求がないかチェックする必要があります。借金の場合も、元本・利息・遅延損害金が正しく計算されているか確認することが重要です。
請求内容に少しでも疑問があるなら、その場で支払わず、必ず専門家へ相談することが安全です。正しい判断基準を持つことで、不当な請求から身を守り、必要な支払いだけを適切に行うことができます。
自分で遺品整理しない方がいい理由と安全な解決策

相続放棄を考えている場合、自分で遺品整理を進めると法律上のトラブルにつながることがあります。特に財産価値の判断や契約関係の整理は専門知識が必要なため、正しい方法で安全に進めるための仕組みや専門家の力を活用することが大切です。
相続財産管理人を選任するメリット
相続財産管理人を選任するメリットは、相続放棄後の遺品整理や財産処理を、専門的な立場の第三者が公平に進めてくれる点にあります。理由として、相続放棄をした相続人は法律上、財産を処分する権限を持たないため、勝手に遺品整理をすると単純承認と判断されるリスクがあるからです。
相続財産管理人が選任されれば、財産の確認、債権者への通知、残置物の処分、賃貸物件の対応などをすべて管理人が進めます。そのため、相続人は法律的なトラブルを避けながら安心して手続きを任せることができます。また、管理人が関与することで、貸主や債権者との交渉も正しく行われ、不当な請求や誤った対応を防ぐことができます。
さらに、複数の相続人がいる場合でも、管理人が調整役となるため、家族間の争いを防ぐ効果も期待できます。相続放棄後の対応に不安がある場合は、相続財産管理人の選任が最も安全な方法と言えます。
専門家(弁護士・遺品整理業者)に依頼するべきケース
専門家に依頼するべきケースは、遺品整理や相続放棄の手続きが複雑で、自分で判断すると危険がある状況です。理由として、故人の遺品や契約内容には法律上の扱いが厳しく、誤って処分したり契約に関わったりすると相続放棄が無効になることがあるためです。
たとえば、部屋に価値のあるものが多い場合や、賃貸物件の残置物撤去が必要な場合、孤独死などで特殊清掃が必要な場合は、個人の判断だけで動くとトラブルにつながります。また、貸主や債権者からの請求内容が妥当か判断できない場面でも、弁護士の助言が役立ちます。
遺品整理業者を利用することで、相続人が財産に触れることなく、安全な作業を行ってもらえる点も大きなメリットです。さらに、専門家が間に入ると誤解や交渉の負担が減り、相続放棄が正しく成立するまでの期間を安心して過ごせます。状況が複雑な場合ほど、専門家に相談する価値は高くなります。
相続放棄の手続きで必ず押さえるべき注意点

相続放棄には期限や取り消し不可などの厳しいルールがあり、正しく理解しておかないと後で大きなトラブルになる恐れがあります。特に手続きの時期や家族間の情報共有は重要なポイントとなるため、慎重に進めることが必要です。
相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない
相続放棄の手続きには「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。これは民法で定められた「熟慮期間」と呼ばれるもので、相続するかどうかを判断するための期間です。この期限を守らないと、自動的に相続を承認したとみなされ、借金や保証債務を含むすべての財産を受け継ぐことになります。
特に、遺品の整理が進まないまま期限が迫るケースや、故人が借金を抱えているか不明な場合は注意が必要です。期限内に判断できないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができますが、この申立ても時間に余裕を持って行う必要があります。
相続放棄は書類の準備や提出にも時間がかかるため、亡くなったことを知ったら早めに情報収集を行い、必要であれば弁護士に相談しながら手続きを進めることで、期限切れのリスクを避けることができます。
一度受理された相続放棄は原則撤回できない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、その内容は原則として撤回することができません。理由は、相続放棄が「相続人としての地位を完全に放棄する手続き」であり、法律上強い効力を持つためです。受理後に気が変わった場合や、後から財産が見つかった場合でも、相続人に戻ることはできません。
また、他の相続人や債権者との関係にも影響するため、軽い気持ちで手続きを進めると大きなトラブルにつながる恐れがあります。そのため、相続放棄を決める際は、財産がプラスかマイナスか正しく把握し、保証契約や借金の有無も調べた上で慎重に判断する必要があります。
どうしても迷う場合は、専門家からアドバイスを受けて、判断材料をしっかり整理することが重要です。相続放棄は取り消せない手続きであることを理解し、後悔しない選択をするための準備が欠かせません。
複数相続人がいる場合の情報共有と連携
複数の相続人がいる場合は、情報共有と連携が特に重要になります。理由は、相続放棄を進めるタイミングや手続きの状況が共有されていないと、思わぬトラブルにつながることがあるためです。
たとえば、一部の相続人だけが相続放棄を行い、他の相続人が状況を知らずに遺品を処分してしまった場合、その行為が「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。また、誰が手続きを済ませたのか、家庭裁判所からの書類が届いたのかなど、基本的な情報を共有していないと、誤解や負担の偏りが生まれやすくなります。
さらに、相続放棄は相続順位が次に移るため、自分たちが放棄すると次の相続人に影響が出ることも理解しておく必要があります。家族間で適切に連携することで、不要なトラブルを避け、手続きを円滑に進めることができます。
まとめ
相続放棄を行う際は、遺品整理や連帯保証人としての責任に関して正しい知識を持つことがとても重要です。相続放棄中に財産を処分したり契約に関わったりすると、法律上「相続した」とみなされ、借金や保証債務まで負担する可能性があります。
また、相続放棄をしても、連帯保証人であった場合や原状回復が必要な場合など、状況によっては対応が求められるケースもあるため注意が必要です。さらに、手続きには期限があり、一度受理されると取り消しができないため、早めの判断と情報共有が欠かせません。
迷う場面が多い相続放棄ですが、専門家や相続財産管理人の力を借りることで、安全に進めることができます。ご自身の状況に合った正しい対処を行い、トラブルを防ぐことが大切です。